お葬式やお通夜のお知らせは突然訪れるもの。そんな時、これって大丈夫?と戸惑うことは多々あるでしょう。状況や環境によって異なる場合もありますが一般常識として知っておきたい知識についてご紹介します。
今回ご紹介するのは、「家族の突然死、警察や病院指定の葬儀社は断れる?」「お通夜の装いについて、どこまでOK?」「告別式の途中退席は大丈夫?」です。
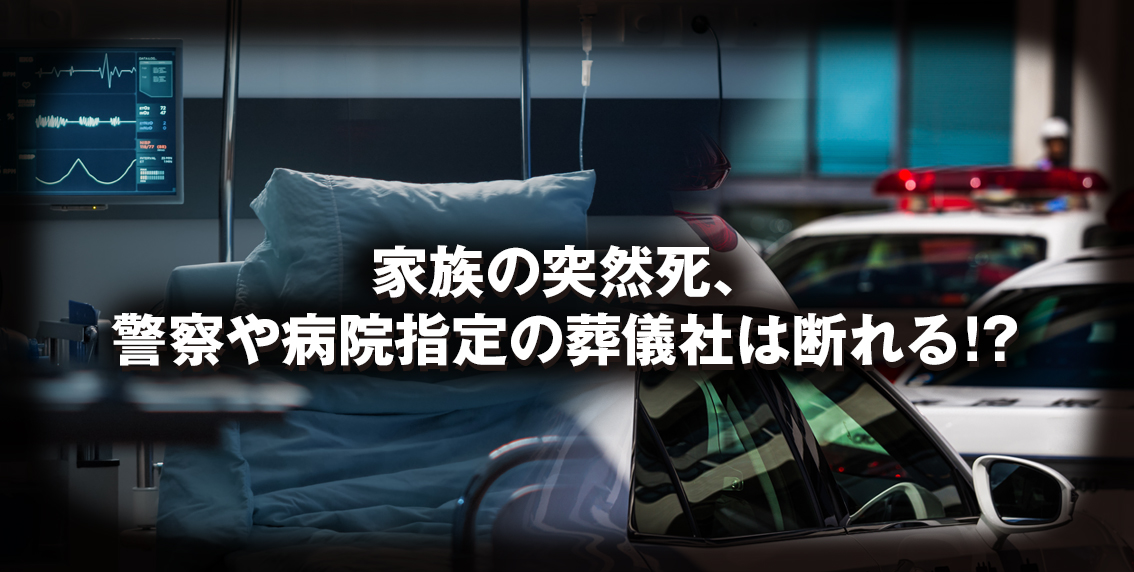
■家族の突然死、警察や病院指定の葬儀社は断れる?
病院で家族が亡くなった場合にまず決めるべきことは、ご遺体をどこに搬送するかです。多くの病院では提携している葬儀社が搬送業務を担当していますので、家族が亡くなった時のために事前に葬儀社を決めていない場合は、病院から紹介された葬儀社にお葬式を依頼することがよくあります。
しかし、紹介された葬儀社にそのままお葬式を依頼する必要はありません。
病院が紹介する葬儀社はあくまで搬送業務を担う業者であり、葬儀内容や方法については特に確認していないことが多いため、費用面で後々トラブルになるケースもありますので葬儀社は遺族が慎重に選ぶべきです。同様に、警察が関与する場合も紹介される葬儀社は搬送業者であり、お葬式まで依頼する義務はありません。
ただ注意が必要なのは、集合住宅や部屋の広さのために自宅に遺体を安置できない場合です。
このような場合、病院や葬儀社から「当社の施設に安置しましょう」と提案されることがありますが、しかし、事前に見積もりや対応の良し悪しを確認していない状態で安置先を決めてしまうと、後で葬儀社を変更するのが難しくなる可能性があります。
もし自宅安置が難しい場合は、地域の火葬場に併設された安置施設などを利用することで、葬儀社の変更を柔軟に行えるようにする方法もあります。病院から葬儀社を紹介された際は、搬送のみ依頼し、その後お葬式の見積もりを取って十分に検討した上で、葬儀社を決めることが重要です。
このように搬送と葬儀は切り離して考え、遺族の希望に合った葬儀社を選ぶことを覚えておきましょう。
■次に家族が自宅で亡くなった場合は?
自宅で病気療養中の家族が亡くなった場合は、すぐにかかりつけ医の先生を呼び、診察後24時間前後の死亡で治療中の病気が原因であると先生の診断があれば、その先生が「死亡診断書」を書いてくれますので、この場合は普通の葬儀手順で問題ありません。
ただ、家族の死を自宅で発見した場合は、警察へ連絡する必要があります。
この場合は、警察により「検視(死亡原因調査)」が行われるまで現場を維持することを求められます。ただし、すべての場合で検視が必要というわけではありません。仮に死亡が治療中の病気によるものであり、死因が明確であると判断されれば、検視なしで「死亡診断書」を書いてもらえます。しかし、治療中だった病気と関連する死ではなく、異常死であると判定された場合などは、事件性が薄くても「検視」が行われます。
■検視とは?
病気などで入院していて症状が悪化し、そのまま病院で亡くなった場合や自宅療養中に病状の悪化により死亡した場合は、医師(かかりつけ医)の判断で「死亡診断書」が作成されますが、それ以外の状況で人が亡くなった場合には、検察官や認定を受けた警察官による検査が行われます。それが、「検視」です。検視は、検察官やその代理人が医師の立ち合いのもと遺体を検査して、身元や犯罪性の有無などを確認する手続きです。
■「検視」の拒否はできるの?
検視は拒否することができません。そもそも「検視」というのは単なる死因の特定だけを目的としているわけではなく、犯罪の可能性があるかどうかを調べる目的もあるからです。そのため、「刑事訴訟法第229条」で、変死やその疑いのある遺体について「検視をしなければならない」と規定しています。
また、「検視規則」により「警察官は遺体や現場の状況を保存するよう努めなければならない」とされており、必要に応じて警察官には遺族に事情聴取をしたり、指紋を採取したりする権限があります。
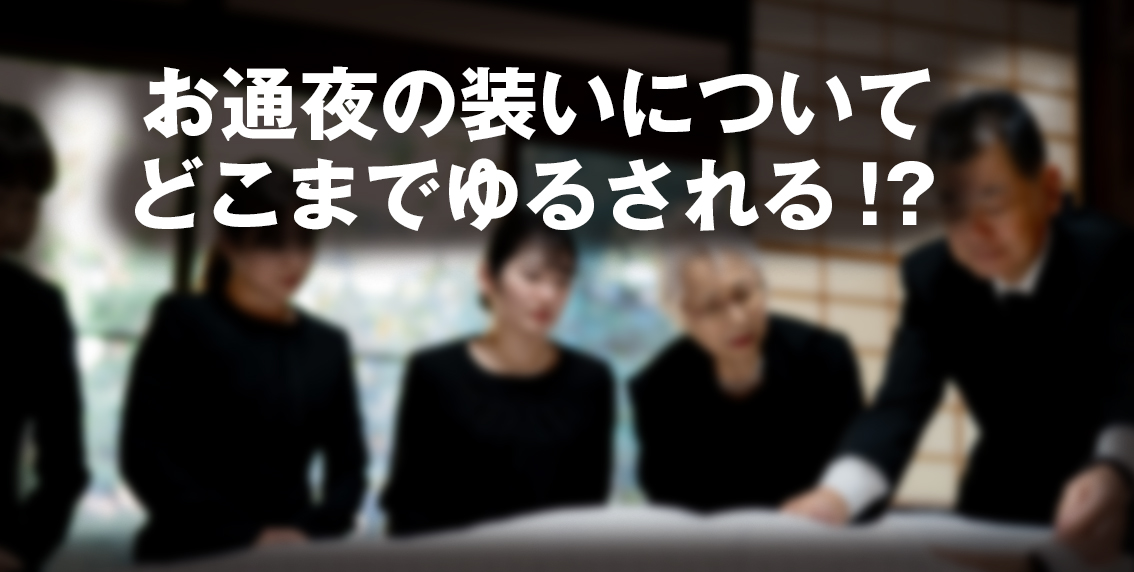
■お通夜の装いについて、どこまでOK?
お通夜は「取る物もとりあえず駆け付けた」という意味合いから普段着でも良いとマナー本などでは記載されていますが、現在は昔と違い携帯電話やメールで訃報が伝わる時代ですので、ご遺族や知人から事前に「いつの何時から葬儀場でお通夜があります」とのお知らせが来ますので、喪服で行かれるのが当たり前になってきています。
具体的には、黒のスーツやワンピースなどの控えめな服装が基本となります。アクセサリーは控え、派手な色やデザインも避けましょう。洋装の喪服か地味な色のスーツが無難です。
■お通夜の服装、基本は洋装の喪服で和装の喪服は控えるべき
地域によりますが、都市部ではお通夜に参列するとき服装の基本は男女ともに喪服です。ただ一点注意すべき喪服は「和装の喪服」です。 こちらは未亡人あるいは故人に近い親族が着るもので、参列者の服装としては控えたほうがよいでしょう。
中には「喪服でもいいの?」と思う方もいるでしょう。確かに、お通夜は「急に」「予期せぬ形で」訪れるものですから、喪服での参列は「まるで準備していたようだ」とか「亡くなることを想定していて失礼だ」と、あまり好ましくないという考え方もありました。しかし、時代とともにお通夜までに時間が空くケースも出てきましたので、そのような風潮もなくなりつつあります。
■喪服を着用する際の注意点
スーツの下は、黒ネクタイと白無地のワイシャツを着用しましょう。弔事用のネクタイがないからといって、そのまま会場に向かうのはタブーです。最近ではコンビニなどでも黒ネクタイやストッキングが販売されているため、もしご自身で用意できていない場合はコンビニなどで買ってから出向くようにするのがマナーです。
■地味な色のスーツは、お知らせからお通夜までの時間が短い時のケース
近年ではお通夜のお知らせがお通夜の数日前に届くことも珍しくありません。しかし、まだまだ急を要するお通夜もあります。お知らせの当日や翌日の場合は参列者としても準備が整いませんので、そのようなときは地味な色合いの平服でも失礼には当たらないと考えています。男性の場合はネクタイの色もスーツに揃えておくことが重要です。 女性の場合はスカートでもパンツでも問題ありません。
■宗派によるお通夜の違い
お通夜は日本特有の風習ですので、キリスト教では本来通夜にあたる儀式はありません。しかし、日本の風習に合わせて通夜にあたる「前夜祭」をおこなうこともあります。故人へ祈りを捧げ、賛美歌を合唱して神父、もしくは牧師の説教を聞きます。基本的に仏式の通夜と変わりありません。
また、仏式や神式のお通夜は最後に「通夜ぶるまい」といって食事やお酒が出される事が、キリスト教の場合は、故人とごく親しい方のみがコーヒーや紅茶でお菓子を食べながら、神父や牧師と共に故人を偲びますので、一般の方は通夜が終ったら速やかに解散しましょう。
近年は「通夜ぶるまい」の規模も縮小気味です。かつては、「お通夜やお葬式に出たら何でもいいので、一口食べて帰るのが礼儀」とされてきましたが、現在は通夜の法要が終ったらすぐに帰っても構わないとされています。ただ、地域によっては「通夜ぶるまい」が盛大に行われているところもあるので、地域の風習に合わせるが無難です。

■告別式、途中退席は許される?
通夜や告別式の途中退席は、基本的にはマナー違反です。 しかし「飛行機の時間が間に合わない」「介護者がいるため長時間家を空けられない」といったやむを得ない事情もあるでしょう。このようなどうしても最後まで参列できない場合は、読経と焼香が済んだ後に場の雰囲気を壊さないタイミングを見計らって退席するようにしましょう。
■葬儀を途中退席する場合のタイミングとマナー
途中退席するベストなタイミングは焼香が行われるときです。焼香の順番が回ってきますので、お焼香が済んだら静かに目立たないように、自席に戻らずそのまま退席する形が一番自然でしょう。神式葬儀であれば玉串奉奠、キリスト教であれば献花のタイミングです。
■遺族やスタッフに途中退席することを伝えておく
また、途中退席することが事前にわかっている場合は、遺族やスタッフに事前に途中退席するむねを伝えておきましょう。葬儀当日は、ご遺族は忙しいので、なるべく当日の連絡は避けて「葬儀の出欠連絡」の際に伝えておくようにしましょう。または、葬儀会社のスタッフに伝えても問題ありません。
